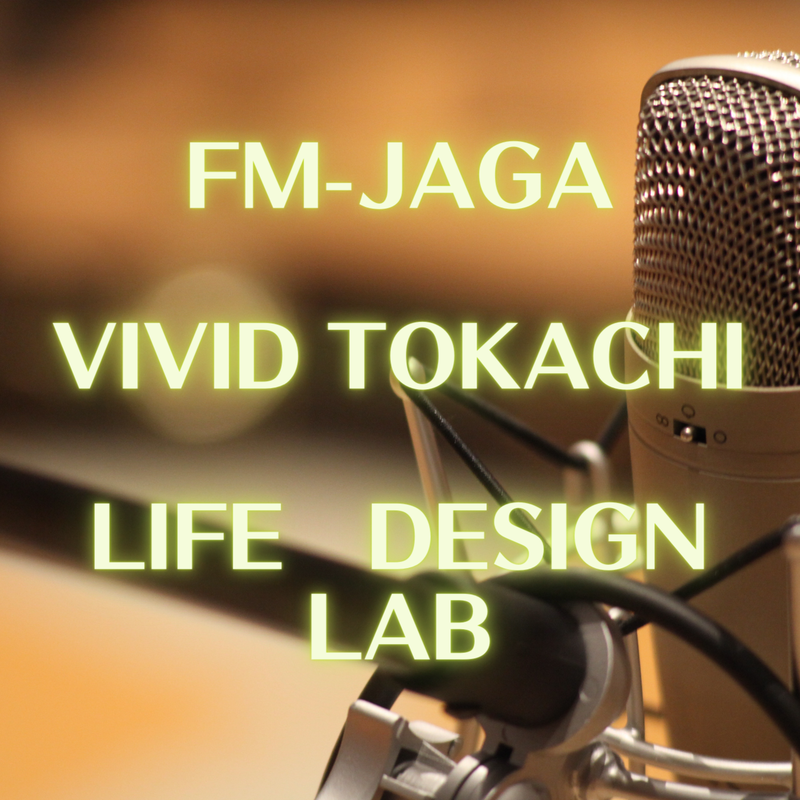|
FM-JAGAのマネーコーナーが新しくなります。 「ライフデザイン・ラボ」となります。テーマは これからの暮らしは自分らしさをデザインする時代、充実したものにするにはお金の裏付けが必要です。自分らしい暮らしをデザインするためにお金ができることを一緒に考えましょう! 4月1日放送分は、 1.今週の気になる暮らしのマネーワード「ベア」 ○今週の気になる暮らしのマネーワード何ですか? ベアです! ○「ベア」ですか?くまさんのことですか? いえいえ、ベアはベースアップのことです。 ○ベースアップのベアですね。なにやら懐かしいような・・・ そうなんです。昔は春闘・ストライキなどがあって、ベアを労働者側が勝ち取るイメージでしたが、バブル崩壊以降は雇用の維持が優先されて給与が上がらない時代が長く続いているのが日本の現実です。ベアというのは員全員の給与を一律で上げる制度です。企業側はその間、ボーナスや定期昇給を実施することで対応してきたんです。 日本人の平均所得は国際比較で1997年には3位だったんですが、今は20番目の水準でもうすぐ韓国に抜かれるところまで来ています。 ○それは衝撃ですね! なにやら過去の栄光にしがみついていた日本が先進国でも後ろのグループに属するようになってしまいました。日本人の平均年収は、1997年から2020年までわずか0.3%の上昇しかなかったんです。でも日本人がそれに耐えられたのは、この20年間物価が上がらなかった。デフレの時代だったからです。他国ではその間1-2%物価が上昇していました。 それが今年は大きな変化が起こりそうです! ○インフレですね。 そうなんです。それに呼応するかのように今年は大手製造業を中心に労働組合のベア要求に満額で答える企業が続出しています。 ○何があったんですか? 業績がよかったことや人手不足、そして「賃上げ税制」が拡大したことです。 ○「賃上げ税制」? 賃上げを行うと、大企業では給与引き上げ額の最大30%、中小企業では最大40%を税額控除を今年度は実施されるのです。企業側にとっても賃上げすることでメリットが発生する仕組みです。ただ税額控除額は最大20%までと頭打ちなのが気になります。 ○いよいよ日本もこれからは賃金が上昇する時代に変わってくる節目が今ということですね。 2.「インフレ・物価高」どう対応する?
○物の値段が上がってますね。 今年の春は値上げラッシュですね。カップ麺も6月から5-10%値上げになるらしいですね。多くの企業は原材料の価格高騰、国内外での人件費の増加、原油価格の上昇による物流費の上昇等を理由に上げています。 ○先程のベアで給料が上がった方ならいいですが、年金で暮らしている方や、なかなか給料は上がらない方も多いですよね。砂川さんこの物価上昇にどうアドバイスされますか? シンクタンクの試算によると今回の物価の値上がりで具体的には1家庭あたり年間5-6万円程度の出費増加になると予測しています。月ベースだと5千円程度の出費が増えると考えられます。5千円程度の目安に節約を考えることが大切です。 ○なるほど!値上げ値上げで、気が滅入るより具体的にいくらと考え対処したほうが気持ちは楽ですね! そうですね。そこはポイントかと思います。 ○では5千円どうやって節約しますか? ヒントは通帳にあります! ○預金通帳ですか? そうです。毎月引き落としになっているもの。電気代・ガス代・スマホ代・インターネット・保険等ありますよね。 ○そこを見直す? 一度引き落としが始まると中身を気にせずそのままという方は非常に多いです。例えばスマホやインターネットは日々サービスが変わります。定期的に見直すべきですがほったらかしになっていませんか? ○そう言われてみると、そのまま放置しているのありますね。 あとはサブスクと言われている定額サービスです。テレビ見放題とか音楽聴き放題とかサブスクサービスに加入したけど今使っていまいものはないですか? ○これも最初は使っていたけど、今は全く使っていないというものも多そうですね。 そうなんです。電気代もいろいろなサービスが出ています。ここも見直すことができますよ。 せっかく機会ですからこのあたりを確認し、月5千円節約を目指しましょう! ○目標額が決まると節約もできそうな気がします!他にアドバイスはありますか? ずばり「地産地消」です。2021年十勝の食料自給率は1339%ですよね。外国の原料の値上がりの影響を避けるには、影響の少ない地元の食材を活用することが大切ですね。今回の物価上昇の原因は、小麦など海外の原材料費の高騰と原油高など物流費の上昇が主な原因ですから。 ○確かに地元十勝の食材を活用すれば、海外の原材料費の影響も物流費の影響も少なくすみますね。 地産地消で物価高の影響も少なくなり、地元の農家さんたちも喜び、経済も回る ○まさに「三方よしですね」!十勝は物価高にも強い土地柄ですね! そのとおりです!
0 コメント
第18回放送分「4月からこう変わる。お金に関すること」
○さて卒業式や終業式、そして4月に入ると入学式のシーズンですね。今日は第18回「4月から変わる。お金に関すること」ということで、4月以降、何が変わるのでしょうか? 今日は18歳成人のお話をします。 ○今年の4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられるのですね。 これからは18歳から成人として取り扱われますので、親の同意が必要なく様々な取引や契約ができるようになります。 ○たとえばどのようなものですか? クレジットカードを作れるようになります。スマホの契約ができます。ローン契約ができます。アパートの契約も可能です。車などの分割払いの契約、保険契約も可能になります。また証券口座開設も可能になりNISA口座の解説も18歳から可能になります。 ○色々できることが増えるんですね。そもそも未成年の場合と成人した場合の大きな違いは何ですか? 未成年の場合は契約行為に親の同意が必要なんです。小遣いでの買い物など例外はあるのですが、親の同意がなく未成年が結んだ契約は原則取り消すことができる「未成年者取消権」という仕組みがあったので、20歳未満は消費者トラブルから守られていました。18歳以降が成人となれば、親の同意が不要となるため契約は原則取り消すことができなくなります。 ○できることも増えるけど、リスクも増えるということですね。 そうですね。懸念されているのは消費者トラブルの増加です。国民生活センターの調査によれば20年度の消費生活相談件数は20歳未満が全体の3%にとどまるのに対し、20代は9%と成人前後でおおきな差がでるんです。 ○それは困った話です。 今までは、お店では未成年の場合、そもそも未成年なので契約できませんと断られたものが、今後はその場で契約が可能になりますので、未成年だからと親があとで取り消しをすることができなくなりますので、注意が必要です。 ○企業側はどのような対応を取ろうとしているのですか? 例えば消費者金融の業者の場合、18歳成人になっても今まで通り親の同意をえる方針とした企業は1割程度、あとの7割は同意を不要とする方針、残りが未定となっています。クレジットカード各社は18歳から原則申し込めるようにするようです。 ○企業によっても対応がバラバラなんですね。 そうなんです。ですからお金についての知識について親が果たす役割が大きくなったといえます。教育の現場でもお金に関する教育が始まっていますが、今の18歳・19歳は十分なマネー教育を受けている状態ではありません。 ○そうですよね。18・19歳のお子様をお持ちのお父さん・お母さんは、どんな話をしてあげればよいですか? まずは今まで話してこなかったお金のことについて積極的に話題にすることが大切かと思います。例えばクレジットカードの仕組みなど基本的なことでよいかと思います。こども目線で何も知らないとカードが打ち出の小槌のように勘違いするケースも多いと思います。住宅ローン・車のローン等ご家庭で毎月どのような支払い方をしているのかなど普段話していないことをあえてお話することは非常に大切です。 新しい契約や大きな買い物については、月々の支払いが小さくても大きな負担になるから、必ず親に相談するルールを作るなども必要です。例えば新学期でひとり暮らしを始めるお子さんとはお金の話をしっかりしてあげてください。 ○成人年齢で20歳まで据え置きのものはあるんですか? アルコール飲酒・喫煙・競馬、競輪などの公営ギャンブルは今まで通り20歳まで据え置きです。自治体が行っていた成人式も20歳に実施を予定する自治体が多いようですよ。 ○なんだか複雑ですね。 以上 「株主優待について知りたい!(その1)」
○さて今日は第16回「株主優待について知りたい!」ですが、株主優待といえば「桐谷さん!」 ですね。テレビでみる桐谷さん楽しそうですよね。株主優待を使って暮らしを楽しむ姿は見ていてもとても微笑ましいですよね。 ○桐谷さんみたいに株主優待を楽しみたいって方、多いと思います。今日は具体的に株主優待について聞けるんですね。 今日は購入の仕方から活用方法まで一通りお話します。 ○お願いします!まずは株主優待ってどんなものがもらえるんですか? 会社によってそれぞれですが、いくつかパターンがあります。まずは自社製品の詰め合わせを送ってくる企業。あとは自社製品や店舗で割引を受けることができる企業。そしてクオカードなど送ってくる企業などですね。その会社の株を買って株主になることが必要です。 ○それは興味深いですね。もう少し詳しく教えて下さい。 例えばデパートだと10%の割引カードが送られてきます。お買い物時にそのカードを提示すると10%割引になるんですよ。 ○それはすごいですね。それはお高い買い物をするほどお得ってことですね。 そうですね。例えばイオンの場合はお持ちの株数によって3-7%のキャッシュバックが半年ごとに返金。いつもお買い物される方にはとても魅力的な優待になっています。 ○お買い物に楽しみが増えますね!レストランやカフェはどうですか? お食事券がもらえるケースが多いですね、年に1回~2回、だいたい2~3000円程度のお食事券が送られてきます。例えば「ほっともっと」のプレナスは2500円分の買い物優待券、マクドナルドはバーガー・サイドメニュー・ドリンクの3種類の無料引換券が6枚ついたお食事券が送られてきます。 ○桐谷さんが自転車で街中を駆け回っている理由がわかりました。株主優待を始めるには具体的にはどうしたらいいんですか? まずは対象の企業の株式を買うことが必要です。具体的には 1.株を買うためには証券会社で口座を開く必要があります。 2.口座が開設されたら、株主優待を受けたい企業の株を買うことになります。 3.株は100株単位で買うことになります。株価が500円の企業の株を買うときは500円×100株ですので、5万円のお金が必要ということになります。 ○なるほど。 4.株主優待を提供する企業の多くは100株単位以上お持ちの方に優待を提供するケースが多いです。但し株数が100株の方の優待、200株以上の方の優待、1000株以上お持ちの方の優待と、お持ちの株数によって優待が変わってくるケースがありますので、気になる企業のホームページなどでしっかり確認することが大切です。 5.注意が必要なのは優待を受けられる割当基準月というのがあります。通常はその会社の決算月やその6ヶ月後、3月決算の企業であれば、3月と9月になります。そのタイミングで株式を保有している方が優待を受ける株主という形になります。 ○株を保有する株数と時期がポイントなんですね。わかりました。次回も、もう少し株主優待について教えて下さい。 次回3月4日は、第17回「株主優待を知りたい(その2)」をお送りいたします。 その12、「イデコでどんな商品を選ぶ?」です。
○前回は、イデコは個人型、他に企業型の確定拠出年金がありその違いについてお話しを聞きました。リスナーの皆さんも、「イデコとNISAどっちがいいの?それとも両方とも始めるべきなの?」と思っている方多いと思います。砂川さんどちらがいいんですか? イデコとNISAのどちらか又は両方やるべきかどうかを考える場合、使い勝手と優先順位で考えていきます。例えば20代のカップルの場合、老後の準備よりもマイホームやお子様の教育資金準備のほうが優先順位は高いですよね。ですから優先順位高いものから準備を進めていくことになります。 イデコは60歳以降にならなければ引き出しができない使い勝手の面では、自由度が低い方法ですから引き出しに制限のないNISAを優先すべきという形になります。 ○なるほど!では子育ての終わった50代の方々はどうでしょう もう既にお子さんも独り立ちの目処が立ち、今後の優先順位は老後の資金確保が最も優先順位が高いはずです。そして65歳という年齢はそう遠くない未来です。使い勝手の面でも特に問題ないです。イデコを利用するメリットは十分ありますね。 ○イデコを利用する場合はライフイベントの優先順位を考え、他に優先するものがあればNISAの活用を中心に、余裕があればイデコも活用、老後の準備が優先順位が最も高い場合はイデコを中心に考え、余裕があればNISAも活用するといった考え方でいいんですね。 そうですね。それでよいかと思います。ただ老後の準備についてはNISAとイデコを併用しても十分とは言えません。NISAとイデコと税制面のメリットはないですが枠以外のの運用手法も考慮すべきです。 ○わかりました。では本題の「イデコはどんな商品で運用すればよいか?」ですが、どう考えたら良いでしょうか まずイデコで投資できる商品ですが、どこの会社でも同じような商品構成になっています。 1.元本確保型 2.債券型 3.株式型 4.バランス型 債券と株式は国内と海外投資に分かれます。バランス型は初めから債券や株式などが決まられた割合で組み込まれたものです。 ○イデコには元本確保型もあるのですね。安心ですね。 いえいえ、そうは言えないんです!以前もお話したとおりイデコは手数料が取られます。元本確保型は減ることはないですが増えることもないので手数料分だけ確実にマイナスです。あるのはイデコに掛けた金額分の所得控除と引き出し時の控除だけになります。例えば税制面のメリットがない専業主婦の方がイデコで元本確保型で運用しても手数料分だけマイナスになってしまいます。 企業型でもそうなんですが、投資経験のない方を中心に選びがちなのは、この元本確保型。これを選ぶとメリットが税制面のみに限られるので、ご自身がどの程度税制面のメリットを受けるのか確認した上で選択する必要があります。 ○一見良さそうなものでも、じっくり検討する必要がありますね。砂川さんであればどんなアドバイスをしているのですか? 投資経験のある方には、株式型一本で、投資対象は世界に分散されたものとなります。 ○株式型一択ですか?リスキーな感じがします。 資産を増やすための近道は、 1.わかりやすくシンプルに投資する。 2.適度に分散させる。 3.それをひたすら続ける。 です。 イデコは60歳まで解約できないのですが、先程はここはデメリットです。とお話しましたが続けるという側面では逆にこの不自由さが大きなメリットになります。「じっくり腰を据えて」投資に取り組みことができるわけです。 株式投資でも例えばアメリカが成長しているからアメリカの株式に投資しようと考えても、例えば3年後の大統領選挙でトランプさんが復活となった場合、どうしようかと考えてしまうかもしれません。世界に投資をするのであれば途中でやめる理由はかなり限定されるはずです。イデコのように「じっくり腰を据えて」投資を続けるには最適ですね。また低金利のこの時代に企業の成長に投資をすることが最も合理的な判断と言えると思います。この手法を淡々と続けていくと老後の資金を増やすことになると思います。 ○ありがとうございます。次回は「初めてみる?投資の勉強法」をお送りいたします。 こんにちは、FA-JAGA「ViViD TOKACHI-幸せな未来のマネー講座」お聞きいただきありがとうございます。お聞きできなかった方や聞いてみたけど?だった方のためにまとめを置いておきます!今回のテーマは 「貯める・増やすの実践法!」 お金はなんとなくでは、なかなか貯まりません。まとまったお金が必要な出来事(例えば、結婚費用、子供の教育費、マイホーム購入、リタイヤ後の年金生活などライフイベント)に沿って準備をする感覚で貯める・増やすを実践するとわかりやすいです。 ○ライフイベントにはどの位お金が必要なの? 結婚(450万円)教育費(1,000万円)マイホーム(3,300万円)リタイヤ後年金生活(月26万円)などとよく言われています。但しこれらは全国平均です。地域によって開きがあるのはもちろんですし、そろぞれのライフスタイルによってライフイベントの金額はかわってきます。 また政府の政策によってもかわってきます。例えば教育費に関しては3つの教育無償化が始まっています。 1 幼児教育の無償化 幼稚園・保育所は、2019年10月からすべての3〜5歳児(就学前3年間)と、住民税非課税世帯の0〜2歳児の利用料が無料に。 2 私立高校の無償化 2020年4月から、私立高校の授業料の実質無償化がスタート。 3 高等教育の無償化。 2020年4月から、大学生などへの「給付型奨学金」と「授業料減免」を、 対象者・金額ともに大幅拡充して実施。 ○ライフイベントは重なります。 教育費とマイホーム(住宅ローン)やマイホーム(住宅ローン)と年金生活など。その場合は前回でもお話をした優先順位をつけることで対応します。一般的には期日が近いものを優先させます。 貯める額を増やすことがたいへんな場合は、目標設定が高すぎるということになりますので、目標を下げて工夫をすることになります。ここでの大切なポイントはライフイベントごとにかかる金額はあくまで平均であり、平均に自分の人生をよせても意味がないということです。今は多様な生き方が求められる時代です。お金を確保することが無理であれば(そもそも無理をすること自体本末転倒になります)、お金をかけないやり方を工夫をすることが大切。それが「幸せ」につながります。 具体的には、「お子様の教育費のことを考えたら購入するマイホームは3千万円でローン組むのではなく2千万円にしよう!」などです。 ○目標額を決めるにはどうしたら良いでしょうか? マイホームを購入する前に長期でお金の収支をシュミレーションしたほうがよいですね。私達はこれを「ライフプラニング」と呼んで、お客様に無料でシュミレーションをかけています。マイホームを購入を検討している方や、リタイヤ前の50台の方などからの依頼は非常に多いです。 ○ライフイベントに沿って貯める・増やすを実践します 具体的には、ライフイベントに沿って「いつまでに」と「いくら」を決めていきます。 例)マイホームの頭金として10年後までに500万円貯めよう! 逆算すると1年で50万円貯めるかたちになります。→50万円貯めるには月4万円弱貯金するぞ! 月4万円はきついなあ!という場合は運用の力を借りながら増やすを活用します。 例えば5%の利回りが期待できる商品で積立をすると月3.3万円ですみます。 7%の利回りが期待できる商品で積立をすると月3万円ですみます。 運用の力を借りることで、月1万円をほかのこと(食事代!旅行代!)に回すことが可能になります。 ○結論 「貯める」だけではなく「貯める+増やす」を実践することで楽しみを増やしながら目標を達成することが可能になります。 資産運用というと、「億万長者を目指す!」などをイメージしがちですが、資産運用を「貯める+増やす」という感覚で3%から10%程度の利回りを目指す形で取り組むことが現実的であり、長続きすると思います。 次回の放送は7月30日(金)10:00-10:10で番外編「FIREって知ってる?」です。 (砂川) 十勝以外にお住みの皆さんも下記の方法で聞くことができます。 1.スマートフォンでの聴取方法 ●android版 Google Playストアより「リスラジ」にて検索し「リスラジ」アプリをインストール ●iOS版 App Storeより「リスラジ」にて検索し「リスラジ」アプリをインストール 2.パソコンでの聴取方法 視聴用ページ(http://listenradio.jp/Home/ProgramSchedule/30016/FM-JAGA)をご覧ください。 聴取方法、詳しくはこちら https://www.jaga.fm/outline_rd.php |
資産形成のことや日々の出来事、思うこと等、お知らせなどを徒然なるままに綴ります。
カテゴリ
すべて
アーカイブ
1月 2025
|